〜子どもの頃からの味、お寺のけんちん汁〜
けんちん汁は郷土料理で、根菜類と豆腐を油などで炒め、お醤油で味を整えたもの、精進料理の定番です。
伝えられている有力な説としては、「建長汁」、「巻繊汁」があります。
建長寺の修行僧が作っていた「建長汁」がなまって「けんちん汁」になった説と
中国から来た、普茶料理の巻繊(ケンチェン-モヤシを胡麻油で炒め、 塩・醤油で、味付けした物)がなまり、けんちんになった説が有力です。

お豆腐と野菜を油で炒めるというところがけんちん汁のエッセンスですね。
私の父の話では、その昔、新潟魚沼地方では、これを油汁(あぶらじる)と言っていたのだそうです。
当時は油は大豆油、とても貴重なものであり、野菜と豆腐でお汁を作り、最後に熱した油を入れたと言うことです。
具沢山の汁物の上に油、寒い冬には冷めにくく、ご馳走だったのでしょう。
そういえば、
島崎藤村の「破壊」の中で出てきますが、「油汁」をけんちん汁と読んでいました。
地域により、少しずつ作り方などが違いますが、ここでは私が子供の頃から慣れ親しんだ、味、母が長年作っていた味の「けんちん汁」を紹介します。
一般的なけんちん汁と大きく異なる点は、お豆腐をとにかく、多めの油で良く炒めることです。お豆腐がポロポロになり、油に濁りがなくなるまで、炒めるのです。
こうすることにより、お豆腐独特の豆くささがなくなり、肉でも入っているような味わい深いものになります。

材料:
干し椎茸 3、4枚戻しておく
木綿豆腐1丁
*入れる野菜の割合は、大根1に対してそのほかのものは半分とする。
大根
にんじん
さといも
こんにゃく
ごぼう
きのこ
*切り干しを少し入れても可。
*精進だし、醤油、みりん、酒、塩
作り方:
1。野菜を切る。
野菜は千切りに切る。
2。里芋は煮溶けることがあるので、小さければ、そのまま、大きければ太めの短冊にきる。
*盛り付けるお椀の大きさを考えて、けんちんの具材の長さを決める。





いかがでしたが?手に入る食材で、野菜をアレンジし、また、作って見てくださいね。



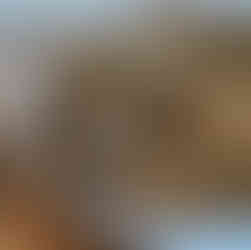



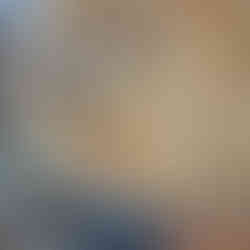



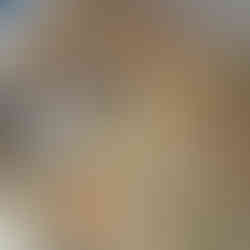

Comments